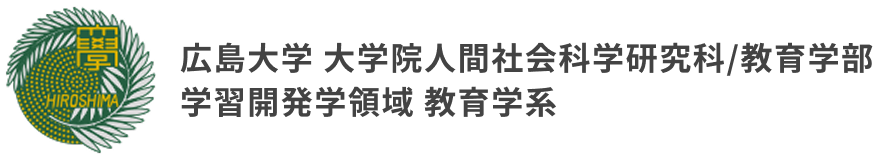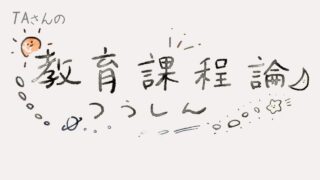2025.04.30
「せとうち」の読書会 2025年度事始め
- #せとうち
2025年の「せとうち」(教育学系ゼミの院生で合同で読書会をする)は,テアハルト, E. 『教授学への招待─教えることと学ぶことの科学的探究』(松田充,宮本勇一,熊井将太 訳), 春風社,2024年 を読むことになりました。
2024年からはじめたこの取り組み,24年度の前半は『教育学年報』の第11巻「教育学の新章」を読んでいました。もともとこの「教育学の新章」は十数年ぶりに10巻以降が出され,その間の教育学の諸分野の変化をレビューした論文集でした。そのため,分野が異なる教育学系の教員と院生で読むにはとても適していました。
24年度の後半はG.ビースタの『よい教育研究とはなにか』を読み合っていきました。これもビースタのいう「大陸的伝統」と「アングロサクソン的伝統」の教育研究文化を比較しながら,また近年のエビデンス重視の世界の中で,必ずしもそれに乗ることができない教育学研究の特質を捉えるものでした。
さて,25年度は何にしようかということで,まずは教員が「おすすめ本」をもってきて,複数の中からえらぶということに。
- アイスナー, E.W., 池田吏志・小松佳代子(訳)『啓発された眼―教育的鑑識眼と教育批評』新曜社, 2024年
- 経済協力開発機構(OECD)(編), 佐藤仁・伊藤亜希子(監訳)『構成と包摂を目ざす教育―OECD「多様性の持つ強み」プロジェクト報告書』明石書店, 2024年
- 中原淳(編)『人材開発研究大全』東京大学出版会, 2017年
- ソーヤー, R.K., 森敏昭・秋田喜代美・大島純・白水始・望月俊男・ 益川弘如(訳)『学習科学ハンドブック 第2版』北大路書房, 2018年
などが取りあげられ,院生たちの協議で冒頭の本に。
解釈が多様にできることから読書会としていろいろな話ができそうだということと,ドイツ教育学が24年度のビースタ本にもよく登場してきたこと。かつ広島大学は教育学(第5類)でたくさんのドイツ教育学系の研究がなされていること。などからの選択らしい。
実際,中を紐解いていくと,「授業心理学」と「教授学」との間をどう歴史的に見ながら違いを論じていくのかなど,学習開発学領域にとっても重要なテーマで述べられ,これまで読んできた蓄積との接点も十分にある。
ということで,今季の最初はこの本になりました。週1で読み進めていきます。
いずれにしても,個人で読むのではなく,複数で読むということの意味は,内容理解だけではなく,多様な「読み」の解釈を重ねていくことにこそ論文の読み方はあるということ。
「正確に理解する」を命題にするんではなく,「私はこう読んだ」「こう感じた」「それはここの文章からだ」というような言葉の重ね合わせをこそ「議論する」という上でも「研究する」という上でも重要だということを学んでいってほしい。そうした読書の力は研究の基盤になるものであり,また「私」をつくっていく上でも重要なので。