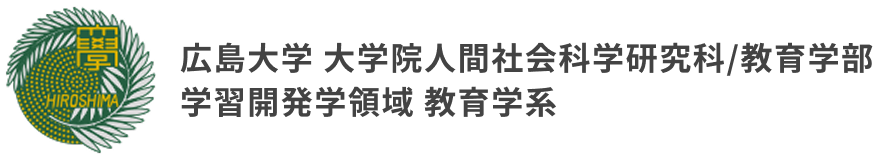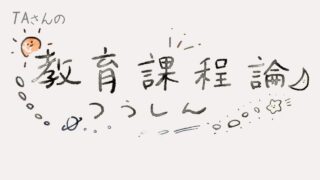2025.05.14
教授学と心理学の結節点はどこにある?
- #せとうち
学習開発学領域教育学系の3名の教員と院生で行なう読書会「せとうち」,テアハルトの『教授学への招待―教えることと学ぶことの科学的探究』(松田充、宮本勇一、熊井将太(訳), 春風社, 2024年)
を読んでいる。
うちの教育組織構成は,教育学といっても多様で,教育史学・教育方法学(含外国人児童生徒教育学)・教師教育学(教育経営学)と分野もアプローチも自然科学的なものから解釈学的なものまで。だからこそおもしろい。
この本はいわゆる教授学と心理学がドイツの教育でどう関係性をもってきたか,自然科学的なアプローチが席巻する中で教授学がおかれた危機感が1つのキーになっている。
とはいえそれをビースタ的に「問題視」しすぎるのではなく,どう共にやっていくかという点がひとつのテアハルトのテーゼのようだ。
この点はとても重要で,往々にして教育(方法)学系からは,心理学や学習科学の席巻に対して,懐疑的な目線が多くなりやすい。実際,僕も末席で訳したビースタの『よい教育研究とはなにか』本も,よく売れてはいるものの,本来ビースタが仮想的に読んでほしいのであろう自然科学的アプローチの人たちには一向に読まれる気配がなく,むしろ教育学の身内に対して「そうだそうだ」と読まれていく向きが強い気がしている。
テアハルトは,ビースタほどに「教えること」を「学ぶこと」から独立的に価値があるものとはせず,関係づけられているという点に立っているからか,教授学の危機なるものを,単に「それでいいんだ」ではない立場で模索している(実際だからこそドイツのさまざまな教育改革の委員長をしていたりするわけで)。
学習開発学という,本来教育学と心理学がいっしょになっている組織で,そもそも教育学のメンバーも多様だからこそリアリティを持って読める。
1990年代の終わりから2000年代の最初にかけて,日本の学習科学の前夜的に『心理学者 教育学を語る』シリーズや『授業を変える/授業をわかる』シリーズのような本が連続的に出て,そこには今の学習開発学のような下地もあったように気がする。ただ,当時はおそらくこれは心理学のメンバーのみによってなされており,今2020年代半ばにあって,教育学と心理学はどういう結びつきができるのかは,僕らの役割かもしれない。
これも合わせて読むと脈絡と意図が捉えやすかった。(というか、ここがないと、第一部がかなり意図が読み取りにくい…)
http://doi.org/10.18926/bgeou/68409 (宮本勇一ほか2025「教育方法学は『教育の学習化』にどう応答するか ― ドイツ教授学との対話 ―」『岡山大学大学院教育学研究科研究集録』)